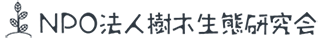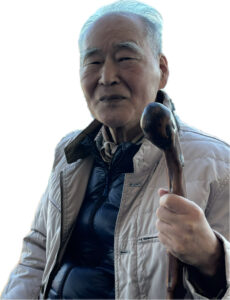林試移植法の想いで
最高顧問 堀 大才
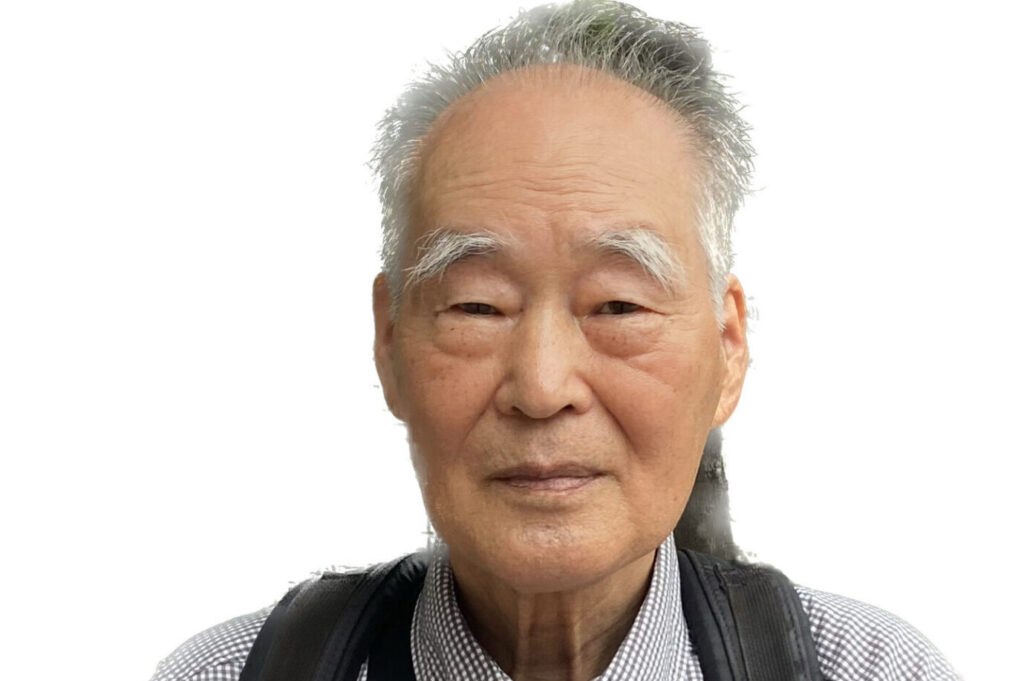
樹木生態研究会の2025年2月23日の総会後の講演(樹木の学校)は、同会理事の直木哲氏が、「神宮外苑再開発報告その1、林試A法による無剪定根回し(90本)の事例」と題して明治神宮外苑の樹木移植について講演した。この講演内容は2024年秋に行われた樹木医学会大会のポスターセッションで優秀ポスター賞を受賞した内容であった。筆者はこの講演に参加できなかったが、直木氏の成功を大いに祝福するとともに、その講演タイトルを聞いて、林試移植法、特林試A法について様々なことが思い出されたので、ここに綴る。
財団法人日本緑化センターが設立されたのは昭和48年(1973年)で、筆者はまだ20代の若手職員であった。日本緑化センターは設立後間もなくして、国庫補助事業(林野庁補助金)として様々な事業を開始した。その中の一つにバーク堆肥と遮根シート(水田用畔シート)を使った大径木の根回し・移植法に関する技術開発試験があった。この技法の考案者は当時国立林業試験場浅川実験林(現在の森林総合研究所多摩森林科学園)長を務めていた植村誠次博士(後に玉川大学教授)であった。植村先生は林業試験場が東京都目黒区から茨城県茎崎町(現在つくば市)に移転するにあたり、林業試験場構内の比較的大きな樹木を安全に移植する技法を模索し、小規模な実験を浅川実験林内の樹木で行っていた。因みに、植村博士はバーク堆肥の開発者でもある。
日本緑化センター設立当時は、日本住宅公団(現在の都市再生機構)が多摩丘陵などで住宅団地開発を盛んに行っていたが、日本緑化センターは伐採されている雑木林の木々を、植村先生が開発中の技法を使えば緑化木として再利用できるのではないかと考え、日本住宅公団の協力を得て、多摩丘陵内の雑木林で根回し実験を行った。作業に当たっては内山緑地建設の協力を得た。
開発試験は数年続いたが、最後に記録を整理し報告書をまとめる作業を筆者が担当した。報告書の纏め作業中に、この技法に名称がないことに気付いた。そこで、植村式樹木根回し法、植村式移植法など、植村先生の名をつけようかと考えたが、植村先生はとても謙虚な方で、自分の名をつけることを固辞されたので林試移植法と名付けることにした。
林試移植法は主に成木を対象とした、移植の前作業である根回しの技法である。林試移植法には3法あり、現在最も普及しているのが林試A法である。A法は一定以上の太い根(開発当初は直径5㎝以上、現在筆者が推奨しているのが直径2㎝以上)の環状剥皮、畔シート及びバーク堆肥を組み合わせて、移植前に細根を十分に発根させて、安全に移植できるようにする技法である。B法は根鉢内の土壌をバーク堆肥(開発当初のバーク堆肥は極めて品質が良く、評判が良かった)に置き換える技法で、C法は根鉢の外に出ている根を、根切りチェーンソーなどですべて切断し、根鉢の隙間にバーク堆肥を詰めて発根を促進しようとする、一般的な根回し法に近い技法である。
林業試験場構内樹木のうち、実際に林試移植法でつくばに移植された木はごくわずかで、現在森林総合研究所内構内の樹木のほとんどは購入木であると聞いているが、日本緑化センターが多摩丘陵で行った雑木林内の広葉樹の根回し試験は一定の成果を得ることができたので、技法を一般に普及するために、筆者の纏めた報告書を、表紙を変えて市販することにした。しかし、しばらくの間はほとんど普及しなかった。
林試A法が最初に大規模に適用されたのは、国立林木育種場(現在の森林総合研究所林木育種センター)の本場が水戸市から50キロ北の多賀郡十王町(現在の日立市十王町)の国有林内に移転する際である 。水戸市の跡地は茨城県が購入し、移転後に茨城県庁が建設されたが、林木育種場は茨城県に対し、移転に際して遺伝子登録している構内樹木すべての安全な移植を求めた。そこで、樹木をより安全に移植するために、林試A法の適用を決めたが、実際に適用されたのは、時間的な制約から300本近い大径木に限られた。根回し期間中は無剪定だったが、運搬の際に、ポールトレーラーからはみ出す枝は切断せざるを得なかったので、無剪定移植という訳にはいかなかった。しかし、その結果は著しく良好で95%の活着を見た。それに気をよくした林木育種場はそれよりも小さな木5,000本の移植を行ったが、根回しを全くしなかった。その結果は無残なもので、ほとんどが枯死したと聞いており、後日、林木育種場の当時の育種部長が筆者に、根回しの有効性についてつくづくと再認識した、と述懐している。
続いて林試A法が大規模に適用されたのは、京都の京都御苑内に建設された京都迎賓館である。迎賓館建設前には敷地予定地内に400本程度の高木性樹木があった。建設に反対する市民団体から、そのすべてを移植保存することを求められたが、幹の腐朽や樹勢等で移植困難な木が何本かあり、実際のところは350本程度の移植であった。移植後に埋蔵文化財調査が急ぎ敷地の大部分で行われるなどの時間的制約から、全木の林試A法適用は困難だったので、成木であるがそれ程大きくない樹木は無剪定直接移植とし、移植先は京都御苑の林内の中に分散した。移植に際し、可能な限り根鉢を大きくし丁寧な移植作業をしてもらったが、その結果は素晴らしく、95%の活着率を得たと聞いている。林内に移植した樹木は全くの無剪定であり、枯れ下がりもほとんどなかったので、1年後には樹木だけを見たのでは周囲にある元からあった木と見分けがつかないほどになり、植え付けの際の支柱、掘り取り跡(草がない)、水鉢の盛り上がり等で移植木であることが分かる状態であった。
林試A法は特に大きな数本の木に適用されたが、ここで筆者にとって苦い思い出がある。林試A法を適用した大径木のうちとても立派なエノキ2本は敷地内の南端にあり、林試A法による根回し後に縦引き(樹木を持ち上げずに、溝を掘ってレールを敷き、油圧ジャッキで根鉢を押したので縦押しか?)で敷地のさらに50m南側に移動したが、移動の前に根鉢の状況を確認したところ極めてよく発根し、工事関係者の誰もが移植成功間違いなし、と思うほどの状態であった。ところが、移植後半年ほど経って、移植木の様子がおかしいので来てくれ、と言う連絡が入り現場に行き、植穴を掘って根鉢を調べたところ、無数に発生していた細根が全く消滅し、臭気が発生していた。原因を調べたところ以下のようなことが分かった。
大径木移植後、京都市は敷地の大部分を深さ2mほどまで掘削し、埋蔵文化財調査を約2年かけて行った。その間沢山の人が穴の中に出入りしたので、穴の底が締め固められていた。調査が終わってから埋め戻されたが、底土が締め固められているので、巨大なプールのように雨水がたまる状態であった。大径木の元々あった場所が埋蔵文化財調査区域内(プール内)であり、大径木移植のために南方向に50mほど溝を掘って行われたが、京都御苑は全体的に北側が高く南側が低い地形であるので、埋蔵文化財調査の後のプール状態のところに溜まった水が大径木移動のために掘った溝を通して移植地に流れ込み続けて、根鉢全体が過湿になり根腐れを発生した、との結論を得た。その証拠の一つに、縦引きせず(溝を設けない)に釣り上げて移植した木(主にマツ)は皆健全に活着したことが挙げられる。
結局エノキの大径木2本は枯れてしまったが、そのようなアクシデントがありながらも、京都迎賓館の仕事では様々なアイデアが生み出され、林試移植法をより効果的な技法にすることができたと考えている。迎賓館建設の際、敷地内にありながら移植でなく現地保存された木もいくつかあった。しかし、建物との関係から、根系の一部を切断せずにいることが困難な木が多かったので、そのような木の太い根は、切断部位より少し根元側で根回しの際の発根処理(環状剥皮と良質な堆肥の施用と遮根シート)と同様な処理を行い、発根後に根系を切断した。結果は上々で、少しの衰退も見られなかった。
京都迎賓館の仕事を終えた後、幾つかの造園会社が各地で林試A法で大径木の根回しを行い移植したと聞いているが、筆者は関わっていない。
京都迎賓館の次に林試A法が大規模に適用されたのは、外環自動車道路の工事に伴い、千葉県市川市北部にある小塚山公園の真下を外環自動車道が通り、その際、工事に関わる区域内の樹木を、別の場所に仮植して更地にし、緑地を深く掘削して道路を整備してから蓋掛けし、蓋掛け後に仮植してある樹木を蓋の上に再移植する、というものであった。その際に地域住民から求められたのは、掘削部分の樹木を全て移植し、道路完成後に元に戻すことだった。実際のところ、2本以上の木が近接して生えていたり、樹勢が悪かったり、樹形がひどく変形していたりして、すべての木を移植することはできなかったが、大部分の高木性樹木を仮植できた。仮植のための根回し期間は無剪定で林試A法を適用した。仮植地は外環自動車道建設予定地の一角としたが、小塚山から仮植地までの樹木の掘り取り運搬には樹木を立てたままで運搬できる機械移植を適用した。機械移植は普通、根回しなしの直接移植であるが、移植木のより高い活着率とその後の樹勢の安定を考え、機械移植の規格に合わせて、根回し時の根鉢を丸くなく最大1辺3mの四角とした。仮植地での成績はとてもよく無剪定であるので、仮植地は自然の木立が再現されたような状況であった。
数年後に、小塚山地区の蓋掛けが完成後、仮植地の樹木を蓋の上に戻す作業が行われたが、そこで問題が生じた。蓋の上にのせる盛土である。当初は外環自動車道路の工事で発生する関東ローム層の表土を植栽用土として使う予定であったが、全体工事の様々な場面で盛土が必要となって蓋掛け上に載せる盛土を調達できないということであった。そこで施工者側が盛土として提案してきたのが、深く掘削したところから発生する真っ黒な泥炭土であった。泥炭土を植栽用土とした経験はなかったが、泥炭土の性質からよく崩して乾燥させて酸素を供給すれば植栽可能であろうと考え、そのようにしてもらったが、別に瓦礫交じりの不良な関東ロームが少々あったので、それを混入してもらった。再移植の際に問題となったのは、仮植地に植え付けた時に遮根シートを使わなかったので、仮植後に根鉢から発生した根の処理であった。普通は、根鉢から発生した根は切断して根巻きを行うが、この時は突っつき工法で対処してもらった。突っつき工法とは、移植後あまり時間が経っていない樹木の最移植を行う場合、埋め戻し土がまだ硬くなっていないので、根鉢から少し遠い所から埋め戻し土を突っついて落としながら根鉢から発生し根をむき出しにし、折曲げ可能な細い根を切らずに根鉢になでつけ、折り曲げるのが困難な根のみ切断して移植する技法である。突っつき工法は東京農業大学環境緑地学科の実習(厚木農場で実施)でその効果を確認していた。再移植の結果は上々で、活着率は聞いていないが、最移植後1年ほどたった時点で現地を見たところ、元々あった森の様な状況であった。
小塚山の森林復元事業と並行して、市川市菅野地区の外環自動車道路予定地内のクロマツの移植も行われた。この地区は昔の砂州で、砂州上に多くのクロマツが植林されたが、その後宅地化して多くのクロマツが個人庭の中にあった。移植の事前作業である根回しに当たっては、ここでも林試A法を適用したが、成績は上々であった。ただ、折角移植した樹木の一部を、全体工事の関係で最移植する場所を確保できず、伐採せざるを得なかったのが残念な事であった。
以上に挙げた事例の他にも、筆者が関係した林試A法による根回し事例は幾らかあるが、その後も技術的工夫を凝らし、現在は水圧穿孔法や割竹挿入法と組み合わせた技法を推奨している。林試A法は筆者が若い頃に開発に関係し、またその後に様々な場面で大径木の移植に適用され、技術的には成功した工法であるので、このように林試A法にまつわる思い出を書くことができて感慨深いものがある。